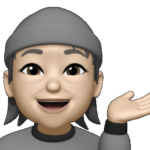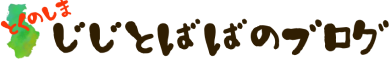学びながら
9月8日(月)晴れ
数日前、裏庭を見ていたらランタナの花がブロック塀を越えて咲いていた。

朝、洗濯をして庭に干した。
「天気も良さそうだし、気持ち良く乾くなぁ」と思っていたんだけど
昼前、庭に出たら・・・あれっ?チラチラ雨が降っている。
慌てて竿を軒下に取り込んで、室内に入ってほどなくチラチラ雨は止んだ。
「ん、もぅ~~夕方まで軒下に干そう」と決め、のんびり落ち着いて食事の準備をしたりした。
雨らしい雨が降らなくなって数ヶ月。
数回だけ、夜中、明け方、昼間に雨が降っていたけれど・・・・徳之島の水源地の水量、大丈夫かなぁ?
水は日常生活に欠かせない。
今は蛇口をひねればジャァ~~と水が出るのが当たり前だけど
ばばの子どもの頃は、各家庭に水道は無く、集落にある泉からバケツに入れた水を担ぐのが子どもの仕事だった。
飲料水も、風呂用の水も・・・・家と泉を何回往復しただろう?
ばばの実家集落は校区でも高台にあるから、泉の水も、底が見えるほどチョロチョロ流れ込んでいた。
そういう時は、窪みに水が溜まるのを待って、2個のバケツのいっぱいになるまで柄杓で掬って入れていた。
大きな松の大木が生えている崖下の坂道を、2個のバケツに水を入れて担いで往復する。
一滴の水を零すのも勿体なくて、ゆっくりゆっくり歩いていた。
水が重いのも大変だったけれど、ばばが一番いやだったのは
季節になると、松の木の下に「マツケムシ?」と呼ばれていた毛虫が無数に落ちて蠢いていたこと。
水を入れたバケツをを担いで、マツケムシを避けながら、ゆっくりゆっくり歩いていたなぁ・・・・
何十回、家と泉を往復しただろうか?と思う。
畑仕事の手伝いもきつかったけれど、「水担ぎ」もきつかったなぁと思い出す。
水道が出来たときも、当初は各家庭にではなく、集落の何カ所かに設置された。
でも、マツケムシを踏むことも無いし、歩いても1,2分くらいの場所に水道があるって
本当に嬉しかった。
ばばの実家は農家だったから、サトウキビ、お米、麦などを作り、自家用の野菜も作っていたので
色々な仕事を手伝っていた。
当時はきつくて、嫌だと思ったことも多々あったと思うけれど
大人になってからは、子どもの時に色々な事を体験したことが、実生活に役立つこともたくさんあった。
家族で、仕事をするので家族の会話も多かったし、両親の働く姿ヵら学んだことも沢山あった。
特に、母は諺など色々教えてくれた。
「正直の頭に神宿る」とか「正直は一生の宝」「天知る地知る我知る」「実ほど頭を垂れる稲穂かな」等々。
子どもの頃は、あまりピンと来なかったが、生長するにつれ両親の教えてくれたことが
「あぁ~こういう事だったのか?」と納得できることがたくさんあった。
自分の幼かった頃の事を思い出すことが多くなった昨今
人間って、周囲から色々学びながら生長するんだなぁと実感しています。
投稿者プロフィール